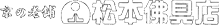講話 「黒白ニ鼠の譬」 平 祐史 元仏教大学教授 浄土宗 海徳寺先代住職
このお話は、私がまだ小学校へ行くか行かないかという幼い子供の時分の話でございました。
私は伏見の片田舎に住んでおりますので、よく私の祖母に連れられまして、伏見の町へ買い物に連れて行かれました。伏見は古い町でございますから、特に大手筋の商店街は賑やかでいろいろの商店があり、その中で仏具などの専門店などもありました。このお店は、たしかお年寄り夫妻の経営している本当に古ぽけた仏具店でした。その店の小さなウィンドウに一幅の絵が掛かっておりました。いつ行ってもその絵がどうも気になりますので、通った時には必ずその仏具店のショーウィンドウ(ショーウィンドウと言ったら締麗に聞こえますが、実際は汚い潰れたようなウィンドウ)の絵を眺めておりました。
どういう絵が描かれておったかと申しますと、その時、私はまだ十歳に達しない少年で、今から六十年ほど前の話でごぎいますのでまったく意味が分かりませんでした。
一人の男が、断崖絶壁の上に一本の立木がありまして、それにまきついております藤のツルにぶら下がっております。そうして断崖の上のほうを見ますと、恐ろしい虎が上から覗いておる。恐らく、虎に追いかけられて逃げ場を失いました男が、断崖絶壁に下がっている藤ヅルが見えましたのでそれにぶら下がって逃れようとしたのですが、下をフッと見ますと水辺で、そのところにはワニが大きな口を開けまして上から落ちてくるのを待っているのでございます。そして四方を見ますと、大きな毒蛇(又は、龍)が四匹おりまして、舌なめずりをして、いつでも「喰ってやろう」と狙っております。そうこうしておりまして気が付きますと、木の枝のところに蜂の巣がありまして、風と男の重さで木が揺れるわけですから蜂がビックリしまして出てまいりましてそのぶら下がっている男の顔の前をグルグルグルグルと舞うわけです。いつ刺されるやら分からんというような状況であります。その上、よくよく見ますとその藤ヅルの根本を、白と黒との鼠が交互に懸命にかじっておるのです。まことに絶体絶命の状況でございます。そしてその蜂の巣から、ポトリポトリポトリと五滴ほどの蜂蜜が落ちてきておる。その蜜を、男は口を開けてなめております。こういう絵が、その仏具店のウィンドウに掛けられておりましたのです。
私はいつもそこを覗いておりまして、祖母に聞きました。「おばあちゃん、これ一体何の絵?」おばあさん曰く「これは地獄の絵や」と、こう言うんです。我々の見聞している地獄の絵は、火の地獄とか水の地獄とか焦熱地獄という、恐ろしい鬼が出てきて亡者を追い回しているような絵を見ておりますのに、どうもこの地獄の絵はまったく性格が違う。不思議な絵だなあと思いながら、日が過ぎてまいりました。
そして私は、昭和ニ十五年に本学へ入学しました。大学の講義の中で、初めてこの話の意味を聞きました。当時、龍谷大学の教授でありまして<唯識学>の大家として知られております深浦正文先生が講義におみえになっておりました。一年間、まったく理解しがたい「唯識論」の講義を受けました。そして翌年は、またその先生から「仏教文学物語」という講義を聴いたわけでございます。その講義の中に、只今申しました「黒白ニ鼠の譬」の話があったわけであます。ご承知のように、この話は「譬喩経」の中に書かれておりまして、文字通り人間というものは断崖絶壁、つまり絶体絶命のところにいつもぶら下がっておる。その命の綱を「黒白ニ鼠」つまり黒の鼠は夜を象徴する、白の鼠は昼間を象徴する、ニ匹の鼠が交互にかじっております。つまり夜が来て、そして明けてまた昼間が来る。それを私たちは毎日繰り返しているわけです。それだけ人間の寿命が縮まることになります。そして上には虎、下にはワニがと、両方から待っておる。そういう絶体絶命の中にありながら、人間は一瞬の愉悦にまかせて、つまりポトリポトリと落ちてくる蜂蜜をなめて自己を楽しんでいるのです。これが、実は我々人間世界の実状なんだということを初めて聞きまして、あの子供の時の<あの話>が、実に大学へ這入りまして初めて、その「黒白ニ鼠の譬」という、「譬喩経」に載っておるという話を知ったわけでございます。
それから私は、この深浦先生の「仏教文学物語」という本を通読させていただきました。この著書は、なんと私が生まれた時に出版された本でありまして、ちょうど七十一年前の出版であります。先だっても読んでおりまして、当時の用語や論調・文章から考えますと、相当読みにくく、むつかしい文章と思われがちですが、そうではなく、今日の口語体で大変分かりやすい文章で書かれております。この本を読みながら、実にこの七十年の私の人生を振り返りまして、何と本当にその通りだと、日一日とその黒と白の鼠が命をかじっていって、太陽が東から出て西へ行けば、なるほどそれで一日が過ぎます。それは非常に穏やかに進んで行くように思いますけれども、逆に考えますと、自分の寿命の限りある人生は一日一日と滅ってゆく、つまり死へ近づいて行くということです。ここで私たちは一体何を考え、何をなすべきかということを、釈尊はお説きになつたわけでごぎいます。
私はそこで思うんでございますけれども、実際、私どもが長い間、大学で、あるいは大学院で勉強をし、更に時間を加えまして今日、学問という世界の中で勉強をさせていただきました。一体何のために己がそういう学問をし、勉強をしてきたのか。知らん間に四十年、あるいほ四十五年の歳月が過ぎ、まさに本日停年退職の<最終講義>をしなければならん。「一体何のために、己は学問をやってきたのか」ということを思います時に、いささか感慨深いものがございます。言い換えましたならば、本当に真理を求めるために、自分の教養のために、自分の真実に生きるがために学問をやっておったのか。それとも、学問のための学問をやっておったのか。一本の論文を書くことが自分の利益・名誉のための学問ではなかったか。論文を書くことによって、講師から助教授になり、助教授から教授になるための、自分の名利のためにやってきた学間であるのか、一体どうなんだろうかということを、改めて今日、この歳になりまして自問しているわけでございます。
ところで、私たちの学問の対象としている領域は、人文科学、あるいは文化科学と言われる領域でありまして、社会に出てすぐさま間にあう<実学的要素>をもっておりません。むしろ、市民生活をする上での「教養人の養成」ということにあたります。このことは、今日の大学を考える上に<学問とは実学か虚学か>というような問題がいろいろとありますが、やはり本学の立場は深い宗教的情操を基盤として薫り高い豊かな教養をもつ人格の育成こそが、これからの新しい大学の使命だと思います。これがやはりその一日一日、白と黒の鼠によって生命もかじられる中で自己の内省をし、還愚にたちかえって養われるその深い教養が次の本当の人生を考えさせるものになるのが真実の大学救育であると信じます。しかし、そのことに思いつくに当たりましては永年の日数がたっておるということも思いまして、私自身まことに慚愧にたえん思いでございます。
以上のような話でございますが、まことに人生のはかなさを言っておりますけれども、一面この「黒白ニ鼠の譬」は、太陽が朝出て、そして沈んで行く。昨日も非常に美しい太陽が西に沈みました。恐らく古代の人たちは、あるいはインドの人たちは、今問題の起こっております<アフガン>の、あの西のほうに向かって、あそこに浄土の世界があるんだと思ったことでありましょう。大阪の人は<夕陽が丘>に立ちまして大阪湾を臨みながら、あそこに浄土の世界があるんだろうと思って眺めたことでありましよう。しかし、あの太陽が沈むことによって、また逆に己の命が一日一日と滅っていっているということも事実であります。お互いにこんなことを思いまして、己自身を大切にし、何のための教養、何のための学間であったかということをここでもう一度考え直して、我々は何をすベきかということをお互いに考えて行きたいと思います。
まさしく本日そのことを、いみじくも唱えました「三帰依文」に、
「人身受け難し、今すでに受く。仏法聞き難し、今ここに聞く。この身今生において度せずんば、さらにいずれの生においてかこの身を度せん。」
と、これこそ、日一日と生命を削られるそれを思い知らしめる言葉ではなかろうかと、このように私は思うわけでございます。
私の法話は、実に今朝をもちまして専任の現役の教授として最後の法話になるかと思いまして、感無豊の思いでお話をさせていただきました次第でございます。どうもご静聴いただきましたことを改めて御礼申し上げる次第でございます。
平成14年1月9日 水曜洗心アワー講話